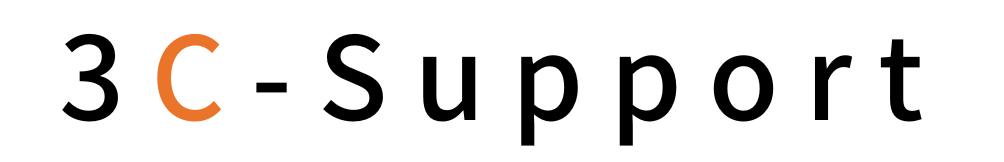12月22日付の『WSJ電子版』に面白い記事がありました。
日本の経済を見るとき、「GDP per capita(一人当たりの国内総生産)」の指標ではなく、「GDP per working-age adult(働く年齢の成人一人当たりの国内総生産)」の指標を使うと見え方が変わると。
日本は成長率が極めて低いイメージがある中で、「GDP per working-age adult(働く年齢の成人一人当たりの国内総生産)」で当てはめると米国とあまり大差はない。
2008年からコロナ前の2019年まででは、G7の中で一番「GDP per working-age adult(働く年齢の成人一人当たりの国内総生産)」の成長率が高かったようです。
働く人の数が減っていく中では、この指標を見ていくとことも有効であると記事は紹介しています。
(記事:「This Stat Could Transform How You View Economic Growth」)
この記事を読んで感じたことは、いかにデータの使い方で見え方が変わるかということです。
データをどう切るか、そのデータをどう見せるかで印象が変わります。
20代の頃、勤めていたグローバル企業でコンサルティング業務を行っていた頃にこのことを学びました。
膨大なデータから、自分たちの提案・主張に合わせて、そのように見えるよう加工する人たちをよく目にしていました。
私が所属していたチームも、多少なりともそういうことはしていたように思います。
経営陣が集まる会議に参加した際に、どの部署も自分たちを良く見せるためにグラフや図を載せたパワーポイントでプレゼンしている光景がありました。
ただ、それらが全て真実を語っていたとは思えません。
データをどう切り、どう見せるか。
この記事でもうひとつ感じたのは、日本経済を悲観しすぎるのも良くないなということです。
人口減少が進む中で全体のGDPが下がっていくのは仕方がないことです。
でも、「働く年齢の成人」に対象を絞った中で成長しているのであれば、それはプラス要素として捉えていきたいですよね。
今日は朝から大きな学びがありました。